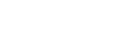第十一章 金融
第一節 無尽講
往時金融機関の発達しない時代に、不時の災禍にかゝり、あるいはその他生活の窮迫に際し、生計をたてかねる場合に、近親や部落の人々に懇請し、無尽講を組織してその急場を切り抜けたのである。だから頼母子講ともいって相互扶助の美しい精神に基づくもので、金や物品(米・茅)の共済融通機関であった。
無尽講は金を主としたが、他に茅とか米などもあった。皆済期限は金品の量と講員の数によって長短があったが、多くは三年、五年の短期間とした。これを構成するにはまず、所要金額、あるいは、物量などによって、一口の掛金と講員数をきめて募集する。会期は毎月開かれる月掛と年四回開かれるのとあった。会場は定座(じょうざ)と、廻り宿とあって、まず講員は会期に掛金を持って集まり、普通一会期に一名だけへ抽籤、あるいは「せり」によって還付されるのであるが「せり」によると、せる人が多ければ手に入る還付金が少なくなるわけである。またせり取った後は会期ごとに一定の高い掛金をかけなければならないから、早く還付金を受取った人程、高い利子の金を借りたことになり、終りになるほど利子が多く手に入る仕組なのである。
古くは加入者の同情心に謝意を表するためか会期のたびに酒食を饗したが、後には食だけになった。
このようにして無尽講は、金融機関の発達しない時代に村の人々の苦境打開に大きな役割を果していたのである。しかし無尽金融は融資上の鉄則である資金の需要と供給が一致するのは最初無尽結成を計画したものだけで、あとの人々は義による偶然性に依存せざるをえないことである。しかも一度当表して無尽を借りると、つぎの融資がきかないことであった。それは封鎖された経済社会ならともかく、自由主義的資本主義経済下では回転率が合わず、新しい金融制度を必要とした。本村においては、大正の始めごろからこれを組織するものがなくなり、そのあとを絶ったのである。
第二節 近代金融
明治十一年(1878年)二月に第一国立銀行盛岡支店、同十二月に第九十国立銀行、この第九十国立銀行は士族銀行と称せられ、盛岡藩士族の金禄公債中心の株券として結集して出来た銀行であったのである。
大正後期の金融機関中、銀行の外は無尽会社と信託会社が擡頭している。
従来、民間に金銭調達の方法として、金銭無尽が組織され、掫り取りや、くじ引きで実施していたが、それが合理的な金融機関として法人組織になったところにこの時代の要求があり、古い無尽制度を現代に活用する端緒となったものであろう。庶民金融としての無尽会社の出現はたしかに便宜であったが、そのため農村民は利用するに前借の形で使い、その返済に土地を押えられることも生ずるに至った。
昭和初期経済界の不況により購買力が衰え、銀行が統合強化されたのであるが、預金者が払出した通り、銀行本来の運営が困難になって金融が梗塞し、商業界も大きくその影響をうけた。ついで大津浪や大凶作によって農山村は大きな打撃をうけた。これらは救済が大きな社会問題となり、その更生が検討されている中に、日本周辺の国際間題が大きくなり、農村更生は、いつの間にか統制経済に焦点を合せざるを得ないようなあわただしい変転を示している。
第三節 貨幣
一 鋳貨
中国銭から和同開珎銭まで
わが国ではじめて金属製の貨幣ができたのは八世紀の初めのことである。それ以前は、現在われわれが使っているような貨幣は用いられず、布とか稲とかの物品が貨幣の代りに使用されていた。ところが、中国では西暦前八百年も前から金属貨幣が鋳造されており、一般に流通していた。もちろん、中国でも最初から金属貨幣が使用されていたわけではなく、今かち三千年ほど前は、自然のままの貝が「おかね」として使用され、後、銅製の貝貨時代を経て、魚幣、刀幣、布幣、環幣というように使用に便利な形態に変った。秦の始皇帝(紀元前246-210年)のときになって、はじめて鋳貨の統合が行われ、円形方孔(形が丸く中心の穴が四角)の銭貨金銀以外の鋳貨に統一された。その後、唐の高祖時代の武徳四年(621年)に開元通宝が鋳られたが、この銭貨が遣唐使などによってわが国にもたらされて、元明天皇の和銅元年(708年)に、これを模範としてわが国最初の鋳貨が鋳造された。有名な和銅開珎がそれである。
しかしまだそのころは、一般民衆は貨幣を使用する知識もなく、その便利さも知らなかったので、永い間の根づよい習慣で、相変らず稲とか布地などが貨幣の代りに使われ鋳貨が造られはしたものの、円滑に流通するに至らなかった。そのため当時の政府は色々な法令を出してこの貨幣を使用させるように仕向けると同時に、和銅開珎が鋳造されて二百五十年後、天徳二年(958年)に乾元(けんげん)大宝が鋳られるまでに、十二種の銅銭を発行して貨幣の流通に努力した。この銅銭は皇朝十二銭といわれ、今もなおわが国初期の鋳貨として珍重されている。
外国銭の流入と徳川時代
平安朝の末期から鎌倉時代にかけて、経済が発展するに従い、貨幣がようやく必要とされる時代になったが、わが国ではそれまであまり普及していなかったので使用すべき貨幣が不充分であった。特に商工業の発達に伴い、貨幣の需要は急にさかんになり少量の皇朝銭だけでは需要を充たすことができなくなったので、高倉天皇の嘉応元年(1169年)ごろから中国銭をはじめ朝鮮、安南などの銭貨が多量に輸入されるようになり、これらの外国銭が徳川時代初期までわが国の銭貨として一般に流通したのである。
豊臣秀吉は天正十六年(1588年)に世界最大の金貨と称される天正大判金を鋳造したが、つづいて徳川家康は幣制に意を用い、慶長六年(1601年)金銀の貨幣制度を確立して大判、小判、一分金、丁銀(ちょうぎん)、豆板銀(まめいたぎん)など五種類の金銀貨を発行した。こうして金銀貨は一定のものに統一されたが、銭貨についてはまだ外国渡来銭が使用されていたので、三代将軍家光の寛永十三年(1636年)に至って“寛永通宝”を法定銭貨に定め、ここに金銀銭三貨制度が完全に確立された。こうして寛文十年(1670年)には外国銭の通用を禁止し、名実ともに貨幣制度が全国的にわが国独自のものに統一されたのである。
徳川時代の貨幣単位は現在のような十進法と違って、一両以下は四進法をとっていた。すなわち一両の四分の一が一分(一切)、一分の四分の一が一朱というように。そして金銀貨は色々の品位のものがあったために、それぞれ交換される相場が違っており、銭貨に対しても銭相場があるというように非常に複雑である一方、丁銀、豆板銀などのように秤(はかり)にかけて使う秤量(しょうりょう)貨幣もあって、今では想像もつかないほど錯雑していた。
このような状態であった上に、徳川五代将軍の元禄時代から幕末の十四代家茂の万延年間に至るまでの間に幣制はますます乱れた。それは鋳貨の需要が増加したのに反して金銀貨が海外に流出した一方、幕府の財政も苦しくなって、財政不足を糊塗するために八回にわたって悪貨を鋳造し、量目、品位を落したからである。例えば、慶長小判と万延小判を比較すると、量目で三匁八五、金品位で千分の二九〇も下がり、おかねの値打ちはなくなって、徳川初期には小判一枚で六俵の米が買えたのに、末期には約一俵余りしか買えなくなった程であった。
南部藩の鋳銭(一倉則文編『近世文古書の手びき』による)
古く慶長のころに密銭が行われていたが、正式に幕府の許可を受けて鋳銭を行なったのは慶応二年大迫で鋳造したのが最初で其後閉伊の栗林、大橋、また梁川でも行なった。
これは寛永通宝四文の鉄銭で裏に、盛字を刻したがまた、無背のものもある。通用は領内限りであったが、無背銭は他領に密輸された。
なお、銭の称呼についてであるが、銭は千文(もん)で一貫匁文(匁)である。実際の目方ではない。法定比価と称呼は一致しなかった。いわゆる時価があった。しかし一文は常に一個で、文と個数は常に一致していた。諸帳簿に記載されている。銭何貫何百何十貫文(匁)は重量で銭価を表したものである。文は匁から出たといわれる。疋は匹ともかくが、これは犬追物で犬百匹を射たものに銭一貫文を与えた。すなわち犬一匹は銭十文に当る。銭一疋(匹) は十文である。しかしこれが銭貨の単位として用いられるようになると種々に変っていった。明治になると一疋は二厘五毛、あるいは二銭五厘で、千疋は二円五十銭また二十五円となった。
この外、砂金についてふれることにする。砂金は、単に砂ともいわれ、古くは各地で用いられたが、近世になると殆ど南部藩特有といってもよいようになった。砂金は両替の場合目方は一割増であった。これを砂金割と称した。すなわち金一両は三匁五分前後であったが砂四匁~四匁五分と替えた。
明治から昭和へ
徳川幕府瓦解後、明治新政府は貨幣制度を根本的に改めることとし、明治四年(1871年)五月「新貨条例」を発布して、従来の両を単位とする四進法を円を単位とする十進法に改正、形も西洋各国の例にならって円形に統一し、本位金貨五種、一円貿易銀、補助銀貨四種、銅貨三種を鋳造した。そして形の上では金本位制を建前としたのであるが、貿易銀はその後、国内に本位一円銀貨として通用したので、実際には金銀複本位制となった。
明治三十年、日清戦争による賠償金を基礎として改めて近代的な金本位制度がとられたが、その後第一次大戦中の大正六年(1917年)には金の輸出禁止が行われ、昭和五年の金輸出解禁までは完全に金本位制度ではなかった。しかも、昭和五年の金解禁は早くも翌六年再禁止となり、銀行券の金兌換も停止されたので、この時を以て実際上金本位制度は停止されたのであるが、第二次大戦中の昭和十七年に日本銀行法を改正する際、形式的にも実質的にも完全な管理通貨制がとられることになり今日に至っている。
この間、現在に至るまでに、多くの金銀銅貨が発行されたが、太平洋戦争中は錫貨やアルミ貨まで登場し、また発行はされなかったが金属素材の欠乏のため粘土を主原料とする陶貨まで製造された。最近では黄銅貨、アルミ貨、ニッケル貨が作られている。
二 紙幣
私札が発生するまで
紙幣は世界各国とも鋳貨ができてからはるかに遅れて用いられるようになったものである。それは紙幣は鋳貨と違って額面価値と素材価値とが非常に違うので、紙幣が流通するには大きな信用または強い権力の裏付けがなければならないからである。しかし鋳貨は重いので大量の携帯及び取扱いに不便であるし、紛失、損耗などのおそれも大きいので、紙幣が自然一般に流通するようになった。
わが国の紙幣はそうしたためばかりではなく、元和年間(1615-24年)に丁銀を適当な大きさに切って使用することが禁止されたので、それまでに切って使用した半端(はんぱ)になった銀貨に対し引替手形が発行され、これが自然に紙幣として使用されるようになったもので、伊勢山田発行のいわゆる山田端書(はがき)がわが国の紙幣のはじまりといわれている。のちになると、町、村、宿、寺社、御所などが私製の紙幣を発行するようになる。
藩札の発生
徳川幕府は幕府の勢力を強めるために、各大名に大きな経済的負担をかける政策をとったので、各大名の藩の財政は非常に苦しくなった。そこで各藩は藩の財政をまかなう便法として、幕府の許可を得て、藩内限り通用のいわゆる藩札を発行するようになった。その発行方法は藩の札奉行のもとに、藩領内の信用ある有力者を札元として発行引換えに当らせたものが多かったが、殆どが金銀準備の裏付けのない不換紙幣であった。藩札の発行額が増加すれば、それだけ公用貨の流通がさまたげられるので、幕府では次第にこれを禁止する政策に変ったが、財政窮乏が激しくひそかに発行した藩もあった。
寛文十年(1661年)越前福井藩が最初の藩札を発行して以来、徳川中期には三百四十八藩のうち二百二十七藩が藩内限りの藩札を発行している。藩札は大別して金札、銀札、銭札の三種で、特定の商品名を券面に表示しているのもあり、また印刷の方法は大部分が木版で、用紙は楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)などを用い、隠し文字あるいは透し入りなど、相当苦心して作られている。
南部藩の楮(ちょ)幣(一ノ倉則文編『近世古文書の手びき』より)
楮幣は藩札である。全国各藩何れも発行した。これが明治維新となり、その処理は新政府の大きな問題となった。
盛岡藩では蔵領切手と称する豪商の発行する一種の手形を藩内限り通用していたが、文政五年(1822年)井筒屋善助以下十一人の発行した領切手の通用を公認し、次いで天保四年(1833年)豪商井筒屋善助、同権右エ門の発行する領切手を公認した。藩では、産物買上のために、御産物切手、一分、一朱、二朱の三種を発行し、盛岡・大槌・宮古その他に引換所を設けて流通し、大いに利益を得たので、さらに大規模の藩札発行を計画し、天保六年十月金二万両を兌換準備金として七福神を印刷した七種の藩札を発行し、先きの井筒屋両家の銭札の通用を禁止した。七福神札と称するもので、二十四文(福禄寿)、三十二文(布袋)、百文(恵比寿)、二百文(大黒)、三百文(弁財天)、一貫文(毘沙門)、二貫文(寿老人)とした。最初は極めて円滑に通用したが、当局は兌換準備金を引上げて他に流用した為藩札の価値も金兌換の渋滞と共に其流通価格が低落し、翌七年四月には正金一両、銭六貫八百文に対し、銭札十三貫文となり、漸次低落して十月には六十三貫文に暴落した。かくて未曽有の天保の大凶作と相まって、藩経済界の大混乱を来し、倒産続出する状態となった。そして八年二月幕府の命に依って通用禁止となった。以来南部藩では藩札の発行は行われなかった。
明治開化期の紙幣
徳川幕府がたおれたのち、明治新政府は財政の窮乏を救うため、明治元年(1868年)四月、まず太政(だじょう)官札を、次いで民部省札、大蔵省兌換証券、開拓使兌換証券などを相次いで発行したが、形式は従来どおりの形であったので、これでは文明開化を唱える明治時代にふさわしくないとされ、明治三年には意匠をあたらしくしたドイツ製の新紙幣が製造され明治五年から使用された。しかし同年には国立銀行条例が発布され、アメリカ製の日本紙幣が流通、その後ようやくわが国でも洋式印刷技術が緒について、明治十年最初の洋式印刷による改造国立銀行紙幣が製造され、十四年には世人の眼を見張らせるような美しい俗に神功(こう)皇后札といわれる紙幣ができるようになった。
明治維新以来、政府は前述のごとく次から次へと色々な紙幣を発行し、しかも殆どが不換紙幣であった上、明治十年(1877年)の西南戦争に当って巨額な不換紙幣を発行して戦費を調達したので、政府紙幣の価値は非常に低落し、このころから政府紙幣と鋳貨との間に打歩(交換価格の差)を生じた。例えば、明治十四年四月には銀貨一円に対し政府紙幣は一円七十九銭五厘にまで低落し、一円の品物を買うのに銀貨ならば一円でよいが、紙幣で買えば一円七十九銭五厘出さなければならないような状態になった。この対策として松方大蔵卿は増税、国費大削減などデフレーション政策を断行し、紙幣の発行量を減らして銀貨と紙幣の打歩をちぢめ、さらに幣制統一を図るために中央銀行の創設を企画して明治十五年十月、今日の日本銀行が開業するに至った。
日本銀行設立以後
明治十八年五月、はじめて、日本銀行兌換銀券が発行され、それまで流通していた各種の紙幣はすべてこの兌換券に代えられることになった。この兌換券は当初は銀貨と引換えられる建前で券面には“兌換銀券”と書かれてあったが、明治三十年、金本位制の採用により、三十二年からは図案様式を代え、“日本銀行兌換券”という名称になり、金貨と兌換されることになった。そして前述のように金本位制度に若干の変遷があったのち、昭和十七年に至り日本銀行条例が廃止され、新しく日本銀行法が公布されて、わが国の通貨制慶は完全な管理通貨制度となり、日本銀行兌換券は単に、日本銀行券という名称になった。
以上のように現在に至るまでに、わが国の紙幣は幾変遷を経てきたが、それぞれの時代に発行された紙幣の紙質や図案などは、いずれもその時代の面影を伝えているのであって、過ぎし日の経済、社会の思い出をよび起してくれる。例えば、最近でも、太平洋戦争時代には紙質は悪く、図案は軍国主義の色彩の強いものであったが、戦後の窮乏時代を経て現在の千円札は良質紙が使われており、印刷もまた著しく進歩したし、図案も民主的、平和的なものに改められている。