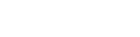第二章 徳川幕府治下における社会的・政治的背景
徳川幕府治下になって、これまで政治関係の文書を司っていた寺僧達に代わり“寺院教育”出身の儒者林羅山(1583-1657年)の手に文書起草権が握られた。羅山は非現実的な仏教を排撃し、儒学とくに朱子学によって実践的道徳を確立した。これが封建秩序に倫理的根拠を与え、幕府政権の正当化を説いたのである。その私塾は幕府から保護され、やがて聖堂または昌平坂学問所として幕府直轄の官学となり「大学」の地位に進んだ。各藩もこれにならい、藩政の精神的、道徳的支柱として儒学を藩士に奨励し、盛んに講座が開かれた。
一方、社会的生産力の上昇期に際会して、農民の生産者は経験を積み重ねることにより、その知識を深め、技術を進歩させ、工業化さえも促し商品経済を発展させた。この理論的根拠として「実学」が形成された。文字を通じて経験を組織化し理論化したわけである。つまり南蛮学(インド・ポルトガル・スペイン)系統の医学や天文学、中国大陸の陽明学などがこれに影響を与えた。八代将軍吉宗が「鎖国」を強化しながら、西洋の学問にある実用性を認め、積極的に奨励した事実は実学の好例である。
しかしこれらの学問奨励は、あくまで幕府の功利主義に基づく、つまり幕府体制をくつがえすようなものでなければ、どんな学問も技術も奨励するにやぶさかでなかったのである。反対にこれをくつがえすおそれのある学問、とくに幕制維持の理論的根拠とした儒学思想を批判しようものなら、幕府は狂気のように禁圧した。前者の例は享保年間(1716-36年)の徳川吉宗世期が、商品経済の発達に伴う封建体制の動揺期であったのに、農民支配を維持してこれをささえようとし、農業技術改良に役だつ学問なら積極的に奨励をした。また鎖国とは無縁でないはずの「蘭学」についても、新知識導入という点から特例を設けて奨励、国防と民生の面に活用したなどがあげられよう。後者の例としては寛政二年(1790年)に老中松平定信が「異学の禁」を出し、同じ儒学でも朱子学以外を昌平坂学問所から締め出している。また同四年には、海国兵談を書いた林子平が政治批判の理由で罰せられ、特例だった「蘭学」にしてもオランダ人との接触を規制し、長崎貿易すら取り締まりを厳にした。それらの飛ばっちりが、高野長英らに及んだことである。換言すれば専制政治家特有の「思想統制」であった。
こうして幕府はその体制を維持する理論的根拠だった朱子学を、家臣や藩士達に強制学習させ、傾きかけた幕政の立て直し役としての人材養成機関を開設しようとした。これが林羅山一族の私塾だった学問所を、公的な学校“昌平坂学問所”に、改編された因である。同時に幕府は蘭書をはじめ農業・土木その他の技術関係書を幕府直営の書庫に集め、その信頼するに足る専門技術者だけにこれを利用させようとした。
このことは新しい知識、学問を幕府ばかりでなく、各藩の指導層がこぞって統治手段としてこれを活用するようになった。つまり封建体制の崩壊を防ぐための人材養成手段として、実学が一層重視されたわけである。これが外国艦船のわが海辺出没期となると国防にそなえる軍事科学の必要性を洋学に求める傾向を助長していき、海外知識吸収熱は一段と高まった。
江戸幕府は国防の充実という見地から、各藩の蘭学に通じたものを集め「蛮書和解御用方」を設けたのは文化八年(1811年)のことである。大槻玄沢がこれに登用されたのであるが、大槻の死後その具申で「洋学所」と改称され「蛮書調所」となり独立した。更に「洋書調所」から「開成所」へと改まり、蘭・英・仏・独・露など各国語の飜訳教授から洋算・物理・化学・絵図など諸学も研究され、総合大学の姿をとりはじめた。これが明治二年に「大学南校」へ、同四年「南校」へと変わり、同五年に「開成学校」となって、東京帝国大学へと変身していった。
洋(蘭)学者たちは海外知識にもとづき、日本の危機的様相をさとり、また政治体制の必然的変化も感得したが、その多くは知識を活用して技術や経営の改革に寄与するという実学の要求にこたえ、政治的変革の主役とはならなかった。つまり洋(蘭)学の一般的傾向が、幕藩の知識吸収の手段とされたからであり、官学化していたからである。従って洋学は一般民衆に根をおろさないまま、明治維新後の西欧科学摂取段階へ移行していった。その先駆的役割りを果たすのは、福沢諭吉の私塾を拡充した慶応義塾である。
一方、幕藩が無力化していった幕末に発展したのは、秋田藩出身の平田篤胤による国学である。本居宜長・賀茂真渕の流れをくむ篤胤は、復古主義と神道主義を前面に押し出し、服従と奉仕を説く政治論をあわせそなえて独自の体系をつくった。これは下級武士の封建制への批判と民族意識の芽ばえにささえられ、他方で農村の階層的秩序を維持しょうとする庄屋・地主層に共感をよんだ。とくに西欧諸国の圧迫と幕藩体制の無力化という幕末の危機を迎えて、尊王撰夷の政治論へ展開し、広範な階層をつかむようになった。
その門人四千三百余、うち三千七百余が篤胤没後の門人であり、文久三-明治三年(1863-70年)まで七年間に、毎年の入門者が百人から四百人を数えたというのでも、その普及ぶりはわかろう。これらの門人が明治維新の変革に主導的役割りを果たしていった。その変革が王政復古という形態をとった処から理解されよう。
しかし“王政復古”というシンボルに結びついていても、国学は必ずしも維新政府の課題に応ずる有効性を持ち合わさなかった。その課題解決の手は、実学から進化していった洋学に握られていたのである。
即ち、慶応四年(1868年)三月、新政府の最初の教育施策として京都学習院(宮廷貴族子弟の教育機関として天保十三年<1842年>に設けた学習所で、弘化二年<1845年>に改称)を復活し大学とする計画があった。つごうで大学になれず“大学寮代”でスタート、これまでの漢(儒)学を主とする制度から王政復古の風潮を反映して国学をも加えた。しかし、政府の東京移転で中絶のやむなきにいたった。
また江戸の昌平学校(幕府の昌平校が新政府の人材養成機関として復活改称)も、同時に復活した開成学校(前身は開成所)や医学校(医学所)をあわせ、兵学の部も加え一本にし、昌平学校と新政府の最高教育機関として、明治二年大学校(のちに大学)と改称した。王政復古の方針にのっとり、国学中心をうたい、有力な国学者が乗り込んで勢力を握ったかにみえた。が、儒学者たちの攻撃が開始されて対立し、新政府も確信ある方針を出しえないまま、開成学校は大学南校、医学校は大学東校として付属的な地位に置かれる外なかった。しかもその後、大学事務当局から文明開花の方向へ改革するよう要求が出されて国学・儒学教官側の反撃があるなどして収拾つかず、大学は一時廃絶の運命となった。
この二つの例からしても国学の優位性をつらぬきえなかったのである。いうなれば変動と対立・相克を繰り返したわけで、このなかから新政府の封建性脱却の方向に合致する洋学が、次第に国学や儒学をおさえ、新しい学校の主導権を握るようになる。
新政府に移行する過渡的現象として、教学界に起った異変がある。幕府がその体制維持のために集めた洋学の俊秀たちが明治元年静岡で沼津兵学校と静岡文学校を経営したことである。江戸開成所にいた西周(にしあまね)や津田真一郎、加藤弘之、外山正一などの逸材が、これに関係した。その多くが新政府に登用されると文学校の方は廃絶されたが、沼津兵学校は付属の小学校を設け、同三年に文学部を併置し、最高学府的な形態をとった。
二年後には新政府の兵部省に移管され、翌年解散したが、この間軍人のみならず島田三郎(民権論者)塚原渋柿園(小説家)田口卯吉(経済史家)清野勉(哲学者)など哲学・政治・思想方面の人材を輩出した。新政府が京都や東京の大学建設にとまどっているときに地方に散った洋学者が、最高学府、つまり実質的な大学を設置したのである。これと並んで福沢諭吉の慶応義塾のように多くの私塾がまたそれぞれの地方で最高学府的地位を保った。
しかし新政府の中央集権的構想が結実するにつれ、人材はこれに登用されて実力を発揮しようと願い、政府の開成学校に吸収されて行き、新しい国立大学を形成するようになる。これに反発して“学の独立”を強調する私学が起ってくる。福沢の慶応義塾や新島の同志社などがその先駆者となるのである。
このような新時代の動きは、各藩にも当然反映した。すでに各藩には人材養成のための藩校があったが、それまでの地域的・郷土的立ち場から進んで国家有用の人材を育成しながら中央と結びつこうとした。新政府もその安定をはかるために人材を必要とした。この態度は新しい大学に各藩から官費生を集める結果となって現われた。
こうして藩学もこれまで藩士子弟だけに限定していた就学制限を解き、広く好学の青年を吸収するようになった。その典型的な例は本県に於ては伊達藩の支藩である水沢留守藩の立生館である。これに関連して“郷学(ごうがく)”も急速にふえていった。郷学を大別すれば、藩学校の支校またはその下部機関として設けたものと、藩主または幕府や代官が領域の庶民子弟を教化するために設けたものと民間有志が設けて藩や幕府の保護監督を受けるものの三種があった。たんに教化というよ。人材吸収がねらいだったが、その経費を藩財政に依存せず、地城でまかなう要素があったので官学や私塾と対比して多分に公立的色彩が強かった。新学制発布と共に公立小学校に移行する素地があったといえよう。
一方、純然たる庶民教育機関である寺子屋も、このころは、社会的制度として、また慣行として、人々の意識の中にしっかり根をおろしてしまっていた。この寺子屋教育だけで満足せず天下に雄飛したいと望む好学の徒は私塾に足を運んだ。ここで儒学の素養を積んで、更に江戸や京都、大阪などへ遊学をした。成業後帰郷して家塾を開き、更に人材育成につとめる者もあれば、帰郷せずに他藩の教官になったり、学者文人として活躍するものもあった。その教科目は伝統的な儒(漢)学を中核としたが、洋学で時代の“明”を開く者もあった。一般に私塾に学ぶものは庶民の間でも上層子弟に属していたが、変動の激しい社会情勢を反映して経済的に恵まれず、苦学力行する者が多く、藩(のちに県)役人に引き立てられて希望を満たす者もあった。とくに戊辰の役で朝敵と目された本県地方には後者の類形が多かった。
新政府もこのような藩学、郷学、私塾あるいは寺子屋などの各種教育機関を利用しなくては、その教育政策を実行に移しえなくなっていた。しかも藩意識や封建的道徳を払しょくしえない風潮を意識して、外見的には政治的刺激を与えないよう配慮しながら、この教育機関を新政府が直接握ろうというのが、明治五年の学制である。