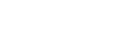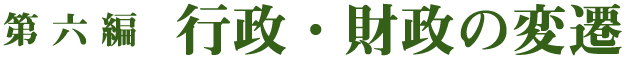第四章 近世南部藩の財政
世界の歴史に驚歎された二百五十年の平和は、人民から自由を奪い、日常の行為、生活の向上を阻止して保持されたのであった。それは家康は、小吏が威光をかりて農民を苦しめた時に「随分と威を張るがよい。彼らがこうされゝば、上の官長はなおさらの事、恐れ入って異心を抱く者はなくなる。百姓を気まゝにする事は一揆をおこす基であるから、鷹匠・鳥見や代官等の非法はたらきは捨ておけ。そうすれば百姓が難儀をするかあ気まゝが出来ぬ。これが慈悲であるといった」といわれている。南部藩の政治も同様で、稲刈りさえも自由に出来なかった。それは検見(けみ)のためである。当時の代官は同時に徴税官としての任務を兼ねていたから、毎年秋になると、村々を巡回して作柄を査定し、これに基づいて税率をきめた。この検見が終らないうちは稲刈りができなかった。だから、場所によっては、氷の張った田圃で稲刈りをする所もあった。稲刈の自由も認められなかった農民は営々孜々あたかも農奴のごとき生活を強いられ、また他を顧みるいとまがなく、徳川伝統の庶民政策である士農工商の厳然たる階級制度の存在と相俟って、地方においても為政者の金科玉条とされ、あくまでも民を愚にしておいて、その上に優越を誇らんとする大名によって、生殺与奪の権を握られ、農民はたゞ米を作り、唯々諾々これを搾取される道具にすぎなかった。
当時村は自治団体の性質を持っていた。もちろん奉行や代官は事務を統轄したものゝ、村には駐在したものではなく、その行政は村役人に依って治められていた。諸税は村が納税義務者であって、年貢を物成(ものなり)といゝ、いわゆる地租に該当したのである。これに対して雑種税を小物成といった。若し、是等未進のものがあれば、その組に割当られた高を納入せねばならぬから、同じ五人組の百姓の負担が増加することとなる。農民は常に正面からと側面から財貨を絞りとられた。
政治は住民の幸福をめざすものでなければならない。個人の力の限界を集団の力によって支えてくれるのが政治である。だが、これは当時の社会には通用されない理論であった。この時代の為政者は住民から搾取を根本とする封建領主であったからである。
領主の搾取は年貢の徴収を通して行われた。当時の田租は、普通に五公五民といわれるように、極めて高率なもので、人によっては六割を越えるものさえあった。災害とたゝかい心血を注いで得た収穫物は、秋になると、その五割が直ちに年貢米として徴収された。従って農民は、再生産資金の蓄積はおろか、飯米にも不足をきたす有様であった。これは、労働に対する正当の報酬ではなく搾取である。このようにして徴収した年貢は、領主自身の諸経費と、諸士の給料にのみ使用された。総てが人件費と事務費で事業費がない。これは、農民が耕作する土地及び山林は藩主のものであったからである。住民の幸福をはからないで、藩主及び同族並びに士族の幸福を確立するのが当時の政治目的であったから、「百姓は生かすべからず、殺すべからず」とか、「百姓とごまの油はしぼればしぼる程出る」とかゞ今日にまで残存している。藩の財政が急迫すると、直ちに田租の外に、御用金、御操合金、寸志金、分限金等という名目でしぼれるだけ搾り上げたのである。冷害や旱魃は天災であるが、搾取は人災である。天災だけでも苦難をなめたのに、さらに人災によって一層塗炭の苦しみにおいやられたのである。
近世南部藩の財政大要を『岩手県史』からひろうと次のようである。
すなわち藩の財政運営に必要な諸経費は、すべて領内から所得されたもので支弁されている。年貢収入・諸課税・現物賦課などで賄われている。
第一は藩の直轄する御蔵入れの土地であり、耕地が主なるものであるが、この外の山林原野や海浜河川も原則的に藩の所有である。寛永十一年(1634年)の内高二十万五千五百五十石中、給所高十万三千六百六十石を除く十万一千九百石ばかりは御蔵領であり、給所高の方は千七百七十石ばかり多い。慶安五年(1652年)は内高二十二万六千五百八十石で、御蔵領は十二万七千四百四十四石でおよそ五六%、給所は九万九千百三十五石でおよそ四四%となり、御蔵入高が増大している。寛文五年(1665年)には八戸藩に表高二万石、内高四万石程度を分割するので、その以後は内容は異って来ることになる。南部重直の相続した寛永十年から寛文四年までは三十二年間であるが、検地高の上にも内容にも数字の上では下のように変っている。
第二は給所地である。寛永十一年の給所高は十万三千六百六十二石で、その給所人員は五百四十一人となっている。その内諸士四百八十七人でその合計高は九万八千七百八十一石、寺社の給所持員数は五十四寺社で、その合計高は四千八百八十一石であった。それが慶安五年には給所持員数が五百四十三人で、寛永十一年に比して、わずかに二人を増しているだけで大差がない。諸士四百八十五人で寛永十一年より二人を減じ、寺社員数は四寺社を増して五十八寺社となっている。しかし内容において大きく変っている。寛永十一年の給所総高は十万三千六百六十石であったのに、慶安五年には九万九千百三十五石であるから四千五百二十五石の減少である。御蔵入高は二万五千五百石以上の増である。それだけに藩庫収入と、給所地と給所持への収入が変ったことが考えられる。
第三は庶民の生活である。承応元年(1622年)の領内人口は二十九万二千二十八人であったとある。従って、南部領内の米穀生産力はこの人口を扶養するだけの量産があったことになる。『郷村古実見聞記』巻三御検地之事の条に、「出穀之内、三箇一は御年貢米、残りニッは百姓之飯料、役金為積候由、御当方穀物出候を考見申候得は、右之積相違無之」とあり、三分の一は年貢、三分の二は農民の所得としてある。これを慶安三、四年ころの検地高二十二万六千五百石の年貢は、三割二分弱の税率で、御蔵・給所の実際収入は七万一千石程度と推算される。この税率を基本とし、仮りに農民収入を六割六分としても十四万九千四百九十石となり、表面では四公六民に近いが、この外役銭、夫伝馬役・現品納入があり、更に郷役と称する町村自治費の負担が加えられるので大体五公五民程度であろう、右の内、御蔵領から藩庫への年貢、その他の課税や収支の大要はどんなものであろうか。南部藩政前期の領内十郡の総石高についてみると、寛永十一年(1634年)には二十万五千五百五十石、その後検地して同二十年には二十二万二千四百五十石、正保四年(1647年)には二十二万二千四百石、慶安五年には二十二万六千五百八十石とあるから、そのころおよそ二十二万五千石程度の総石高をもっていたと考えられる。二十二万五千石の総石高から、どれだけの年貢収益があったかを推測すると、慶安三年には三割一分七厘三毛であったとあり、するとこの年の収益は七万一千石を越していたと思われる。その後、延宝・天和の八年間(1675~1682年)の平均引合は三割二分七厘七毛であるから、平年作収益を三割二分七直として計算すると、二十二万五千石の高から七万三千五百七十五石の収益があったことになり、七万三千五百石前後の米穀年貢は、藩の倉庫と、地方諸士その他の給人へ納められ、年間生計の中心をなしたことが考えられる。
年貢収益の外に、御役金銭の賦課をやっている。参勤交代のための蓄積費用としての舫金、江戸御供走夫・同詰夫金・御小者金・御材木金・馬買衆入用金・馬飼料、などの名目で金銭を徴収している。その額は年間どの位であったか明記したものがないが、公的費用として全貌から徴収したであろうと思われる。江戸御供走夫・同詰夫金・御小者金・御材木金を百石当り二両一歩宛としても、二十二万五千石の高では五千六十余両、馬匹関係の入用銭は四千二百六十余貫文、これを一千両と換算し、舫積立金二千二百五十両と合せると八千三百両を越すことになるが、どうであろうか。
この外現金収入の面では鉱産税・林産税・畜産税・染料薬科移出税・諸営業、その他があったが、年間総額を判然と掴むことは至難である。後年の享保年中には「御国中一ヵ年御納米七万五千駄余、御役金は五万五千両余」(享保九年「御倹約大目録」)とあるに参稽括されるのである。
支出の面では、藩主の上下に数百人で江戸往来に要する諸費用、藩主の妻子及び江戸常府のもの、諸入費、江戸盛岡間の物資輸送に要する海陸の諸入費、夫伝馬の諸入費、道路橋梁の修理費、河川の渡岸や水路の修理、開墾入費など、対外関係のものがまず考えられる。
次は行政上の施設として、居城やその他の城郭や諸役所・倉庫・船舶の修繕と作料があり、その賄料や扶持料があろう。
行政面では、藩の家老以下、諸役付の諸士その他の役付のもの、手当、諸賄、外来者の接待、年間諸行事の出費があり、臨時出費を要する不時のできごともまゝあったであろう。この中には藩主一族の消費する出費の歩合は、少ないものでなかったであろう。以上収入では年貢・役金銭・現金、支出では対外・施設・行政の関係であるが、それについて、寛永十年以後の藩財政について以下その大要を窺うこととする。寛永年間から享保初年ごろまでを藩政前期として扱い、享保末年あたりから藩政後期として扱うこととして、藩庫収入の御蔵領の年貢、全領からの課税や支出、給所の年貢、御役金銭、あるいは一般庶民の生活にも関係する諸郷役について記述するが、その詳細について窺知することは至難である。ことに藩政前期の記録資料は湮滅しているし、藩政時代、藩財政の収支を詳細に記した筈の勘定奉行の諸記録は、公表を憚かったのか、他の原因によるのか伝わっていないことである。天正十八年(1590年)豊臣氏政権下の大名としてその領土を安堵して以来、明治元年(1868年)までおよそ二百八十年間同じ領土を統治したので、寛永十年以降(二百三十余年間)といえども、ともかくも一通り藩財政の動きや経済状況が窺い知られるのは幸いである。
藩政の後期の財政は、藩政前期に比較すると、困難苦痛の連続であった。第一に農業生産力の向上は見られなくなったこと、第二に鉱産開発による産金が減退したこと、第三にその他の林産・畜産・水産も行詰りを見せたことが指摘される。
産業が不振であるにかゝわらず、藩経営に要する諸経費は節約できない面もあった。たとえば幕命による諸費請の費用、領内飢饉への救助、蝦夷地や領内海岸の防備の如く不可避的出費が生ずることになる。
藩では、元禄の飢饉と産業の不振によって、享保年中には財政不如意となり、享保四年(1719年)には諸士中より七ヵ年間、禄高四分の一の借上げを布令したが、享保七年には江戸屋敷のみで総額十余万両の借財を生じたという。
享保八年の春、七戸長右衛門・松尾吉右衛門・沖弥市右衛門等を挙用して、財政経理の元締とし、経理を委ねた。沖弥市右衛門は財政通として知られ、その上『御倹約大目録』『御倹約小目録』は有名となった。そのため諸役所の統廃合や、役人の整理が行われ、冗費節約が断行され、諸士の俸禄の四分の一の借上も停止された。しかし享保十年六月、藩主利幹(もと)が病死し利視(み)が藩主になるに及んで、享保十一年三月元締役沖弥市右衛門が家老等に排斥され永暇となり江戸に去った。先代の倹約令が弛緩して、藩財政はさらに窮乏し、紊乱するに至った。「御倹約大目録」によると、領内生産の米穀の総量はおよそ八十八万石余と推定され、人口一人宛が一石五斗程度を消費し、十五万石近い数量は味噌と馬の飼料、十三万石程度は酒造用として消費するという。領内生産の九八%が自領で消費され、わずかに一・六%が他領へ出ていたことになる。また年間収入の金銭は十五万両であり、その収入の半分は民間の消費であった。
米穀二駄を米の一駄七斗四升で計算すると一石四斗八升になるから年間三百六十五日に割っても一日四合となる。金額三十七万の人口を扶養するには米一日四合程度を必要とするとして五十四万七千六百石を要した筈であり、雑穀を含めて八十万駄五九万石あったかも知れない。
森博士は『岩手を作る人々』の中で、財政に窮乏した藩は天保十年(1839年)、全領内に軒別役という新税を起したと述べている。
軒別役賦課中は他の新税御用金を徴収しないという条件で、五ヵ年間軒別役を賦課することにした。これは一軒当り一貫八百文を標準として、肝入役、老名、下役代官の目利によって賦課額を定める一種の戸数割である。細民に対しては二分の一軒分、三分の一軒分、豪家に対しては百軒分、二百軒分と財力に応じて賦課し、合計一ヵ年に二万九千百八十両を賦課した。それを通別割当に見ると、一、三千八百両盛岡城下、一、二千五百両大槌通、一、二千五百両宮古通、一、二千両三戸通、一、二千両福岡通、一、千八百両野辺地通、一、千四百両花輪通、一、千両鬼柳・黒沢尻通、一、八百五十両安俵高木通、一、八百両五戸通、一、八百両二子、万丁目通、一、七百八十両上田通、一、七百両日詰・長岡通、一、七百両沼宮内通、一、七百両野田通、一、六百五十両八幡・寺林通、一、六百両見前、向中野通、一、五百五十両大迫通、一、四百八十両飯岡通、一、四百両沢内通、一、三百両徳田通、一、二百五十両厨川通、一、二百二十両雫石通、一、二百二十両七戸通一、百八十両大更新田となっている。
従来なれば、盛岡城下の次は和賀・稗貫地方だったが、今度は宮古・大槌通となったことは、漁村の振興に着用したためである。
ところが、この新税を賦課している間に、他の新税を徴収しないと言明しておりながら、もう二年もたゝない中に、年三-四回位新税を課したり、御用金を徴収したり、さらに勘定所切手、金所預切手を発行して藩の支払いに使用したり、米雑穀預切手、年貢運上金を担保として利付債券を発行して引受を強制し、峻烈な取立を行なった。殊にこれは漁村に対して大規模に行われた。
さらに、山村地帯から大豆の安価な買上げを行い、その輸送料を支払わずに江戸に送って、江戸藩邸の経費に充当させた。これが為に他国に出稼ぎに出る者、財産を二束三文に売払って逃散する者、小作名子被官になって隷属する者、扶持食、添人として他家に身を寄せる者が多くなった。
弘化四年(1847年)十月二日、藩は全領の農民、町人一統に対して、臨時に六万両の御用金を命じた。軒別を賦課する時に、五ヵ年間御用金その他の新税を課さない条件であったのに、またまたの巨額の御用金である。
遂にたまりかね一揆を起したのであった。
次に『南部叢書』五の邦内貢賦記から本村分を拾いあげてみる。
盛岡五代官竝鵜飼御役立之品々
一、正月御礼金 百石 砂金弐歩宛肝入壱人六り宛
一、同 御立木 百石に付拾駄宛
一、同 蘭莚 同 壱枚宛
一、同 菅莚 同 壱枚宛
一、同 へリナシ 同 壱枚宛
一、ワラ莚 同 弐枚宛
一、草ボウキ 同 弐本宛
天和二年(1682年)?
一、高千九百十三石四斗
土渕村 三つ五分七り八毛 高四百二十一石五斗八升七合
鵜飼村 三つ二分七毛 同三百八十八石七斗四升六合
滝沢村 二つ一分八毛 同弐百給三石九斗四合
平賀村 一つ一分三り三毛 同三百四十六石三斗九升三合
平賀新田 一つ三分一り七毛 同弐百十七石七斗八升五合
右何も弐分之増歩加候得は引合弐つ四分三り九毛
米〆四百六十六石六斗六升六合
一右惣高之内千弐十石五斗九升弐合諸役御免地御物成は上納
鵜飼御蔵 二つ(横三間長七間 縦三間長七間)
一、高五千七百九十石四斗六升七合
栗谷川 三つ四分七り五毛 高千七百八十石弐合
上太田村 四つ九分一り五毛 同千七百弐十石八斗三合
大釜村 三つ九合三り六毛 同八百弐十三石三斗九升
篠木村 四つ四分三毛 同五百七十壱石八斗三升九合
大沢村 四つ五分三毛 同六百弐十五石九斗八合
大沢川原村 二つ一分七り一毛 同弐十石五斗六升二合
栗谷川
野新田 同弐百四十七石九斗七升三合
右何も二分増歩を加候得は引合四つ一分八厘五毛
米〆弐千四百弐十三石五斗九合
一右惣高之内百拾弐石六斗九升五合諸役御免御物成は上納
(なお、第四編農民生活の変遷、第二章、第十節納税、一の年貢の基礎と二の租税の種類を参照せられたい。)
江戸期には金・銀・銅の貨幣があるから、それについて簡単に説明すると、金貨・銀貨・銅貨青銅がある。金貨は十両大判重銀四十五匁・一両小判同四匁八分・二分判金・一歩金・二朱金・一朱金の六種があり、一両の金貨は、普通に砂金五匁と同額に取引きされていた。一朱金なら十六枚・二朱金なら八枚・一歩金なら四枚・二分判金なら二枚が一両で、次第に小形から大形になっている。
銀貨の場合も一朱、銀十六枚・二朱銀八枚・一歩銀四枚が一両であった。金一匁は銀十匁と同価とされた。しかし、銀貨五十匁(一歩銀四枚)の含有する銀は正味四十匁銀八割銅二割とされた。
土地の売買などに代価を幾切と書く場合は、一切とは一歩銀一枚のことであり四分の一両である。一歩金銀は同額であるから、二歩は一両の二分の一で、二歩とは半両の代名詞として用いられていた。
砂金取引の場合は、重量本位で貫目であるが、通貨との換算では五匁を一両としている。たとえば砂金十五匁なら三両、十七匁五合なら三両二歩となる計算方法である。
金貨・銀貨のことを金(かね)と称したが、金に対して青銅貨を銭(ぜに)と称している。これは青銅で鋳造した穴あき銭で、寛永通宝が主なるものであるが、その一枚を一文(いちもん)とよび、千枚で一貫文(いっかんもん)と称し、以上十進法となっている。金一匁の価格は銀十匁と同価、金一匁と銅千匁は同価、従って銀一匁粗と銅百匁は同価ということになる。また、銅銭には前代から永楽銭(えいらくせん)がある。徳川幕府のはじめ、前のような公定で、銭四貫文は金一両に換算され、米一石は貫文とされていた。しかしこれはあくまでも原則であって、物資需給の如何により、社会経済の動きや変質によって、その貨幣相場もそのつど、そのつど変っている。『封内貢賦記』に「金壱両之目形五匁也。金壱両銀目ニシテ六十目。永銭壱貫文ハ金壱両二替也。永銭弐百五拾文ハ金壱歩ニ替也」とある。天和年中の基準であろう。